学部・大学院FACULTY TAISHO
CATEGORY
国際文化コース
人文学科国際文化コースで学ぶこと⑩ 文化研究とSDGs
前回、SDGsの2021レポートを英語で読んでみることを提案いたしました。単に英語の学習のためにSDGsを題材にしてほしいと思ったわけではありません。
人文学とSDGsはじつは密接なかかわりがあります。
頭ではわかっていても、格差も差別はなくならず、地球上に豊かな地域と貧しさにあえぐ地域があり、その不均衡がなかなか解消されないのはどうしてなのか、人びとの意識にまで入り込んで深く探究するのが人文学(Humanities)であり、文化研究です。
春学期に3年生たちといっしょにEdward Saidが書いたCultue and Inperialism(1993)のなかの一つの章、”Jane Austen and Empire”を読みました。Saidはこの本よりもOrientalismという本で一般的には知られているかもしれません。大航海時代以降のヨーロッパにおける帝国主義、植民地主義がどのような文化的影響を残したか、ということをさまざまな物語的言説をもとに分析するのがCultue and Inperialismですが、”Jane Austen and Empire”では、いまでも繰り返し映画化される19世紀初期のイギリス人女性作家Jane AustenのMansfield Parkの物語構造を分析することによって、宗主国と植民地の関係を読み解き、その意識や価値観が帝国全盛期を過ぎ、もはや植民地への経済依存がかなわなくなったあとも根強くイギリスに文化として残ったことをSaidは丁寧に論じます。
学生たちがSaidの説く宗主国と植民地の関係をよく呑み込めない様子だったので、このような質問をしてみました。「皆さんの手は、皆さんの頭がかゆいときはかいてくれる。顔に汗が出れば、手はハンカチで拭いてくれる。それでは手に悪いなあ、と思って、手がかゆいときに頭はかいてあげますか。手が汗すれば、顔はハンカチで拭きますか」と。
学生たちは笑いました。だれも手に悪いとは思っていません。
それと同じ感覚が宗主国にはあったとSaidは論じるのです。あまりにもあたりまえすぎて、意識することもないようなことだと論じるのです。意識することもないことだから、文化的価値観のなかに根強く残っていると論じるのです。
リベラルな考えをもつことは社会的な活動の前提です。それでも、どれほど公正でありたいと思っても、偏見にとらわれたい姿勢でいたいと思っても、私たちはいつのまにか、意識にすらのぼってこない自動的な価値判断にとらわれているかもしれません。
SDGsを考えるとき、データだけでは見えてこないものもあるはずです。2021レポートのさらに奥に考察を進め、私たちを取り巻く地球環境を文化的に探究してみませんか。簡単に答えの出ない探究です。だからこそ取り組みがいのある探究です。そして現代に生きる以上、この探究から私たちは逃れることができません。
大正大学人文学科国際文化コースの学生たちが実践しているのも、このチャレンジに取り組み、探究することです。
Saidの文献を英語で読むのも難題でしたが、テクストは原語で読みたいという学生は一生懸命に英語で読みました。日本語翻訳の助けを借りた学生もいました。語学の力は一人ひとりの学生によってさまざまです。オールラウンドな英語力をつけたいという学生も、幅広く文化研究をしたいという学生も、それぞれの得意な力を発揮してディスカッションをしました。
Saidの理論を用いて、日本の漫画やアニメーションを分析することができるという興味深い報告もたくさんありました。
その紹介はまた回をあらためて行いたいと思います。
いま、私たちがいる時代をグローバルな視点で鋭く分析し、自らが見出したテーマに新たな探求を実践するために、国際文化コースの学生たちは楽しく研究を進めています。
余談になるかもしれませんが、Mansfield Parkの物語展開は、200年を経た現代の若者である学生たちにも興味深いものであったようです。主人公Fannyははたして幸せになったのか、この物語の結末はハッピーエンディングといえるのか、という話題でも盛り上がりました。夏休みの一興に、映画化もされていますので、楽しんでみてはいかがでしょう。
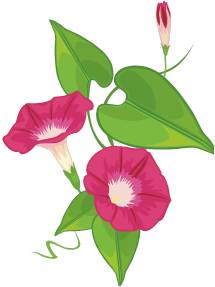
国際文化コース
