大学紹介ABOUT TAISHO
「第二の開学」
―次の百年に向けた大正大学のビジョン―
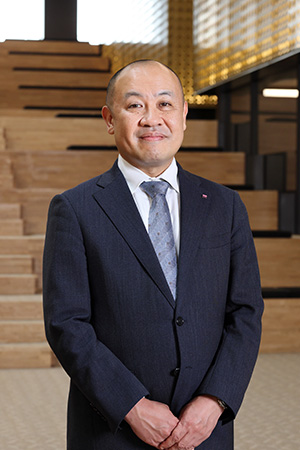
令和5年11月1日に大正大学の第37代学長に就任しました神達知純です。
大正大学は大正15年(1926年)に開学し、まもなく創立百周年を迎える歴史と伝統のある大学です。大正大学は仏教連合大学構想を創立の由縁とし、大乗仏教の精神である「智慧と慈悲の実践」を建学の理念とし、「4つの人(慈悲・自灯明・中道・共生)となる」を教育ビジョンとしています。
「智慧と慈悲の実践」は菩薩の生き方を表しています。菩薩とは自らの修行の完成と衆生の救済を志す人を意味します。わかりやすく言えば、自己の研鑽に励むとともに、他者の幸福を願って行動する者です。こんにち多様性や利他が話題となっており、菩薩のような生き方に共感が集まっています。
私は建学の理念「智慧と慈悲の実践」および教育ビジョン「4つの人となる」に改めて光を当てて、それらに基づいた大学運営に熱意をもって臨みたいと考えています。
いま大正大学ではどのような教育が行われているでしょうか。 本学は、建学の理念に示されるように、実践的な教育を伝統としてきました。近年では「地域戦略人材」の育成を目標に、実践的な教育にますます力を入れています。地域や企業との連携関係を構築し、キャンパスとは異なる学びの場(フィールド)が充実してきました。教室で学んだことをフィールドで活用し、再び教室に戻って学びを深める。このような理論と実践の往還は、学生の学びに大きな効果をもたらすばかりでなく、人間的な成長にもつながっています。
また、大正大学では高大社接続の視点を重視しています。高校と大学、大学と卒業後の社会はそれぞれ別々ですが、ひとりの人間が成長する過程においては連続しています。近年の大正大学は高大接続の研究に力を入れ、高等学校との実質的な教育接続を共創してきました。また全学共通教育を再編し、社会で活用できる汎用的な資質や能力を身につけることを目指す教育を展開しています。
変動の激しい時代と言われています。このような時代であるがゆえに、高校から大学へ、大学から社会へという時間軸において、一人ひとりの学びと成長を支援していく必要があると考えています。大正大学では総合的な学修支援体制を構築し、教職員とチューターが学生の学びと成長をサポートしています。
大正大学の建学の理念は菩薩の生き方を表していると述べました。大学に在籍している間だけでなく、生涯を通じて菩薩のように生きてほしい。本学の建学の理念には、そのような願いが込められています。
令和8年(2026年)に、大正大学は創立百周年を迎えます。この節目を「第二の開学」と位置付け、次の百年に向けて、新たな大正大学の未来を築いていきます。
2023年(令和5年)11月1日
大正大学 学長 神達知純
