学部・大学院FACULTY TAISHO
CATEGORY
日本文学科
第37回「おうだい子ども日本語教室」の開催
|
2024年5月25日(土)に、第37回「おうだい子ども日本語教室」を開催しました。だんだん日差しも強くなり、夏が近づいてきました。今回は、小中学校の運動会シーズンということもあり、参加人数は少し少なめの小学生と中学生併せて9名でした。 |
|
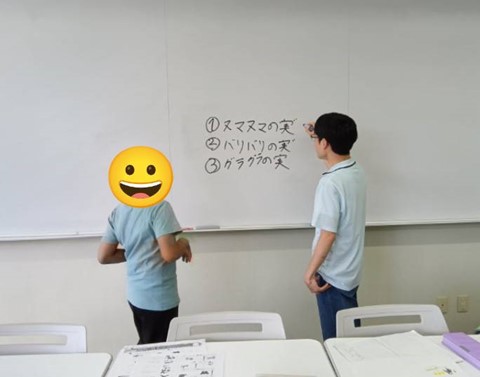 |
|
|
|
|
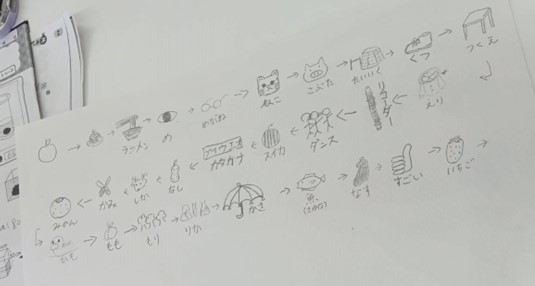 |
|
| 三枚目の写真は、カルタを使った日本語の学習の様子です。学校で使う言葉や動作が書かれたカードで練習したあと、カルタ形式で再確認しました。かなり白熱していました。ただ机に向かうだけでなく、こうした遊びの要素を取り入れることで、飽きずに楽しみながら学ぶことができたようです。 |
|
 |
|
ここからは中学生の学習の様子です。こちらのグループでは、文を音読したり問題を解いたりしながら、それまで理解していなかった単語や、間違えやすい漢字などを理解する活動をしました。漢字は音読みと訓読みの使い分けが難しいようです。 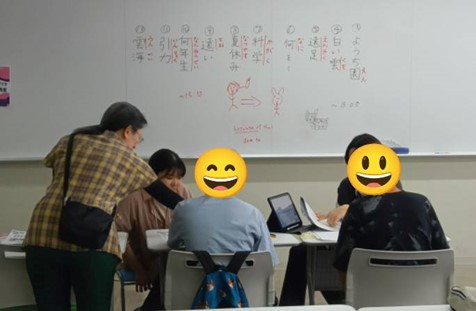 |
|
次の写真は中学2年生の数学の学習の様子です。6月に定期考査があるため、試験前に勉強したいというリクエストに応えて、同じ国出身の留学生である大学生サポーターが、時々フォローしながら勉強を進めていました。  |
|
| 学生サポーターのコメントを紹介します。毎回色々な工夫をしながら手ごたえを感じ、また、次回への課題を見つけている様子が分かります。 ・今回は、前回の反省を生かして、日本語の勉強に重点を置いてみました。生徒本人も日本語をもっと頑張りたいと感じていたのか、本人の意思で休憩時間や遊びの時間を減らして、勉強を頑張ってくれました。文の中に1つ知らない言葉があるだけで、思考が止まってしまうことがあるので、ことばの一つ一つを生徒と確認しながら、文章の理解を手伝う活動を今後も続けていきたいと思います。 ・小学生に 対応しました。最初はカードを用いてコミュニケーション活動を行いましたが、かたくなりがちで、もう少し柔らかくコミュニケーションしたいと感じました。その後、ワークをやりましたが、漢字の読みや語彙で躓く部分をどのようにフォローしていったらよいか、今後の課題を感じました。後半は折り紙をし、いきいきと作品を作ってくれましたが、折り紙の時間ばかりになってしまったので、今後は、「この時間は○○をする」等の区別をはっきりつけて、切替えをうまくつけていきたいと感じました。 ・初回の教室で緊張した様子でしたが、好きな漫画の話題で会話が盛り上がった結果、授業の半分がクイズになってしまいました。今後は、好きなものを尊重しながら、楽しいと思える範囲で為になる日本語を教えて行けるように工夫したいと思います。 今回も、小・中学生の参加者も大学生サポーターも、それぞれ生き生きと活動していました。今回初めて参加した小学生 やサポーターもいましたが、ベテランのサポーターがフォローしながら、楽しく日本語を学び、交流できる空間が作られています。 |
|
| 38回もすでに実施済みですので、追ってご報告できればと思います。次回の教室は、6月29日(土)の14時から16時までです。 参加希望やお問合せは、「odaikodomo.taisho◆gmail.com」までお寄せください(◆を@に変えてください)。 |
|
| 大正大学文学部日本文学科では、これからも様々なイベントや取り組みを行っていく予定です。日本文学科公式SNSアカウントにおいて、情報発信をしていますので、良かったらフォローや拡散のほど、よろしくお願いします。 | |
| 大正大学文学部 日本文学科 | |
