学部・大学院FACULTY TAISHO
宗教学専攻
【宗教学専攻】日本宗教学会第83回学術大会に参加しました

会場の天理大学
2024年9月13日(金)~15日(日)、天理大学杣之内キャンパス(奈良県天理市)にて、日本宗教学会第83回学術大会が開催され、本研究室からは教員および院生が参加しました。
大会第2・3日目には個人発表とパネル発表が行われ、本研究室からもOB・OG含め多数の関係者が発表しました。
まず、個人発表から紹介します。
9月14日(発表時間順)
◆髙田彩先生(國學院大学)「信仰を継続させるための工夫-宗教者の日記分析を中心に-」
本学講師でもある髙田先生は、武州御嶽山において、現在、御師が講とどの様な関係を結び、維持・継続させようとしているのか、御師の自筆の手帖と関係者への聞き取り調査を元に、コミュニュケーションに着目し分析・検討されました。
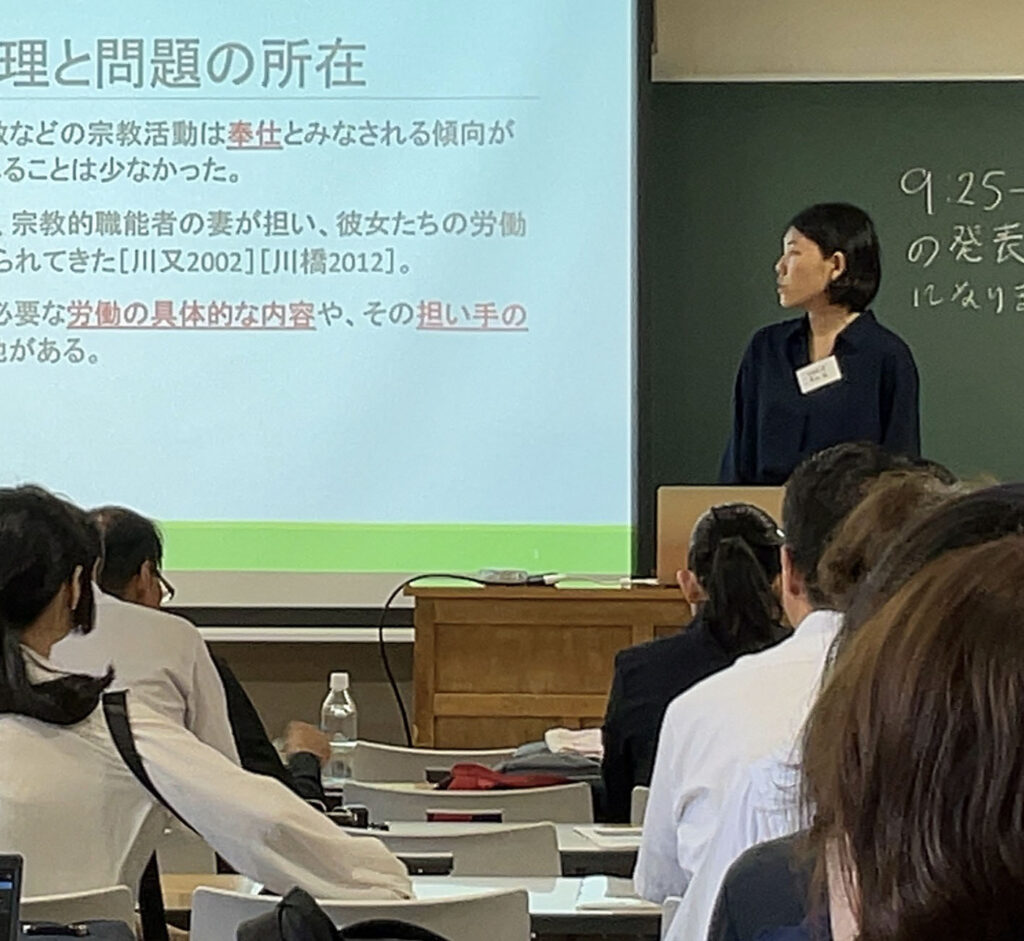
◆大澤広嗣先生(文化庁)「聖地の高等教育と仏教者-旅順高等学校長の川瀬光順-」
OBの大澤先生は日露戦争(1904-1905年)の激戦地として聖地とされた遼東半島旅順で奉職していた高等教育のスタッフに、宗教者としての聖性が求められていたのかという点について近現代の戦争に伴う人為的な聖地形成の観点から検討を行いました。
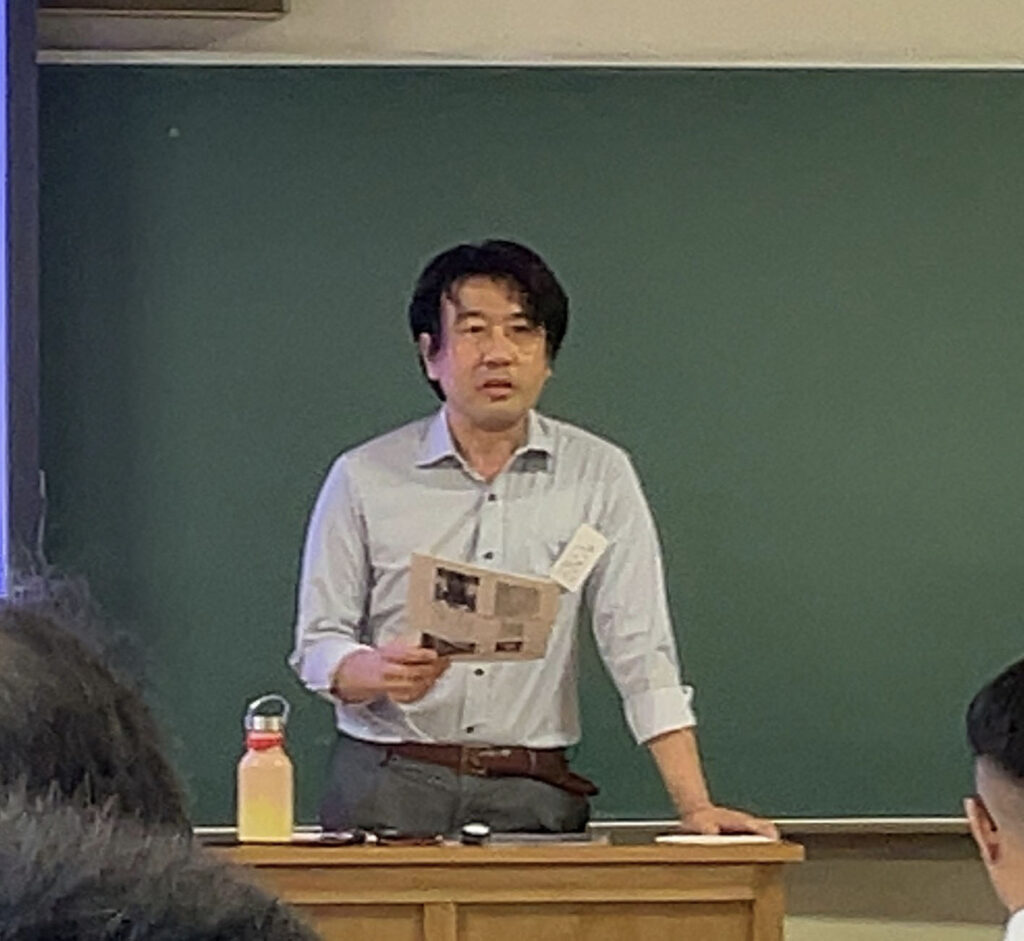
◆小前ひろみさん(本学院生)「原田治郎の美術解説にみる仏教-1910 年『スタシオ』誌より-」
博士後期課程の小前さんは、クリスチャンである原田治郎が英文美術雑誌『スタジオ』誌に1910年に寄稿した日本美術の英文解説から、仏教的な表現が用いられたことに着目し、どの様な解説をし、なぜ仏教概念を用いたのかを考察されました。
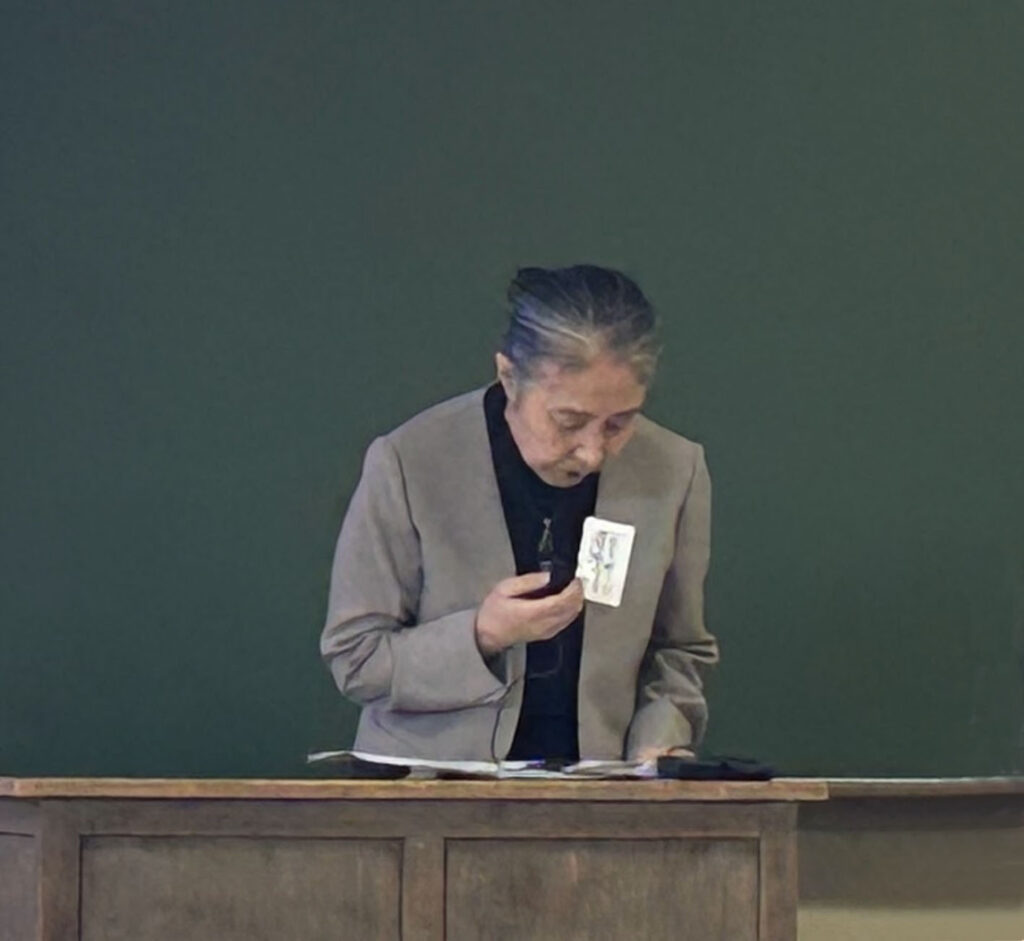
◆弓山達也先生(東京工業大学)「日下部四郎太と信仰物理学(信仰佛利)-没後 100 年の検討-」
弓山先生は、東北大学理学部教授の物理学者日下部四郎太の没後100年を期し、日下部の提唱した「信仰物理学」について、主著『信仰佛利 二人行脚』を中心に、日下部が関わった研究や論争も踏まえ、日下部が何を解明しようとしていたのかを検討されました。
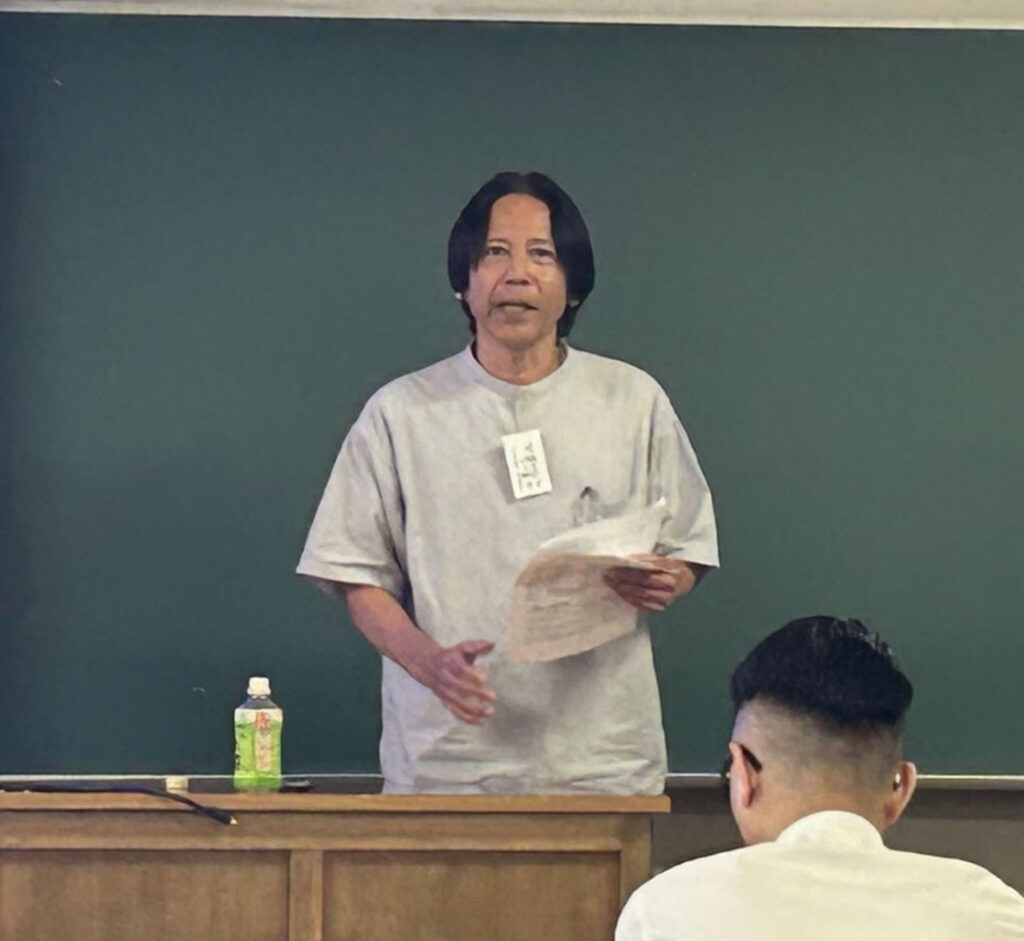
パネル題目「日本のアニメ・特撮と宗教」(代表者:松野智章先生)
◆松野智章先生(東洋大学)「アニメの中の神と神々―宗教理論の応用として―」
OBの松野先生は言語相対主義の枠組みの「溶解」という問題提起を基盤にし、一神教と多神教の表現の違いに注目して、アニメというメディアによって具体的に、どのような情報の共有がなされはじめているのかという点について考察しました。
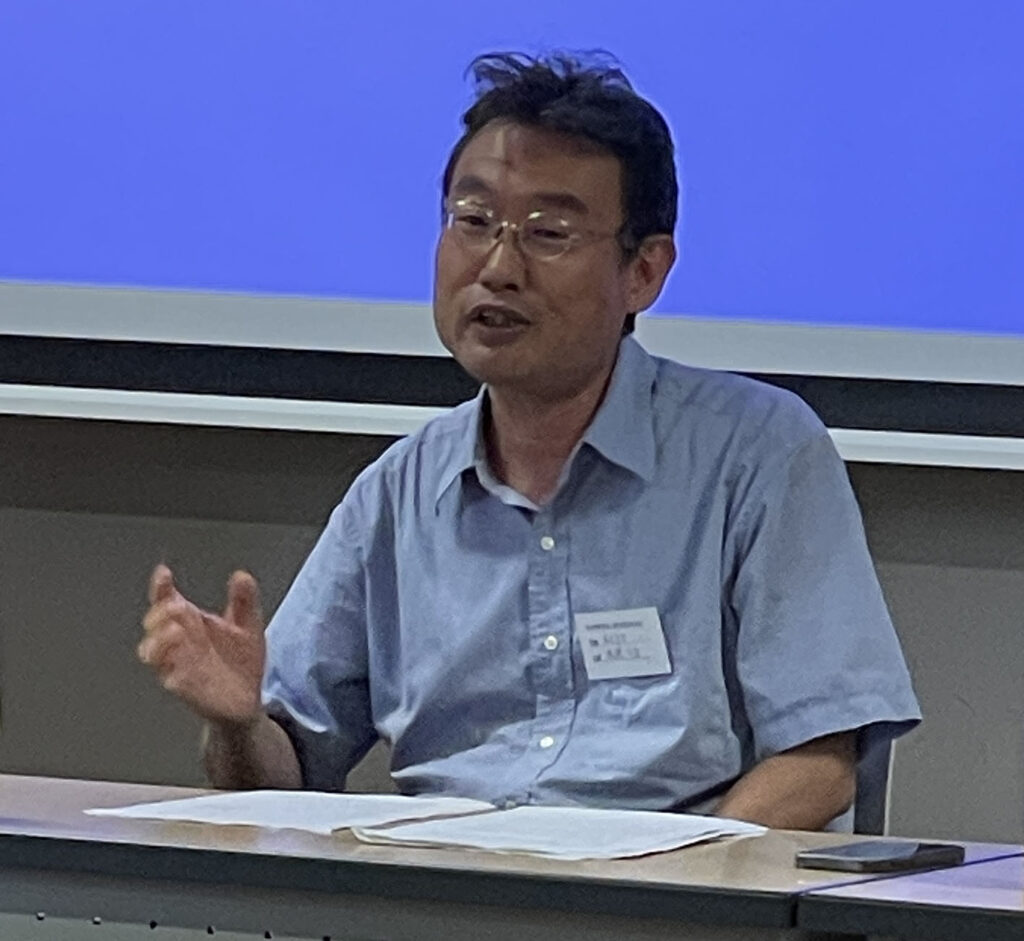
9月15日
◆高瀬顕功先生(本学准教授)「ポストコロナにおける葬送儀礼の実態-寺院向けウェブ調査より-」
髙瀨先生は本学の地域構想研究所BSR推進センターが2023年に実施したウェブ調査の結果をそれ以前の調査結果との比較と共に、ポストコロナの実態分析をおこない、儀礼の簡素化傾向や、都市部とそれ以外の地域での変化における質的差異などを報告されました。

◆芳賀徳仁さん(本学院生)「顕彰会の天皇観」
博士後期課程の芳賀さんは仏教系の新宗教である顕彰会の研究をしています。本発表では、顕彰会の発行した機関誌や新聞などから天皇に関する言説を跡づけ、思想水脈としての戦後の日蓮主義的国体論の特長を検討しました。
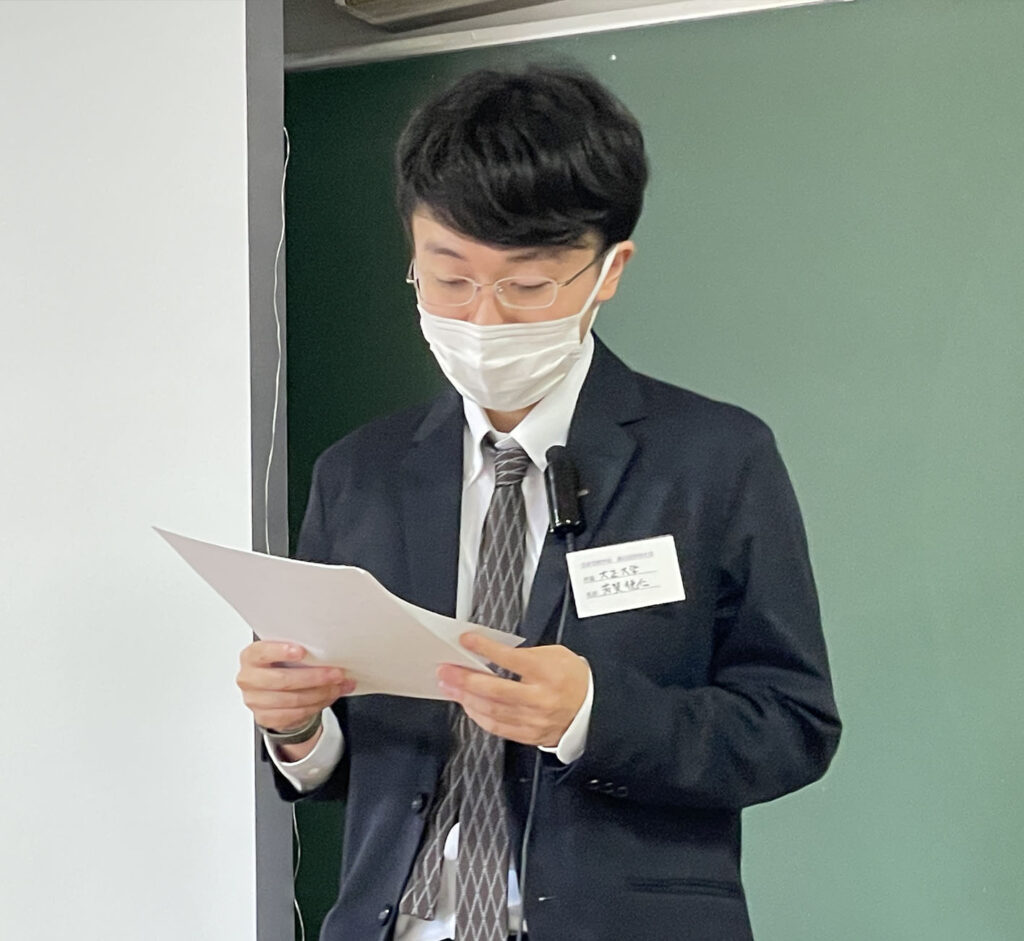
パネル題目「地方自治体が引き取る死者たちの現在-全国アンケート結果から-」(代表者:山田慎也先生)
◆大場あや先生(日本学術振興会)「いかに死者たちを引き取るのか―儀礼の側面から―」
本学講師でもある大場先生は、全国の自治体を対象としておこなった「引き取り手のない死者」についてのアンケート結果の中間報告から、火葬や埋葬などの際に、自治体がどのような儀礼対応をしているのかについての実態報告と考察をしました。
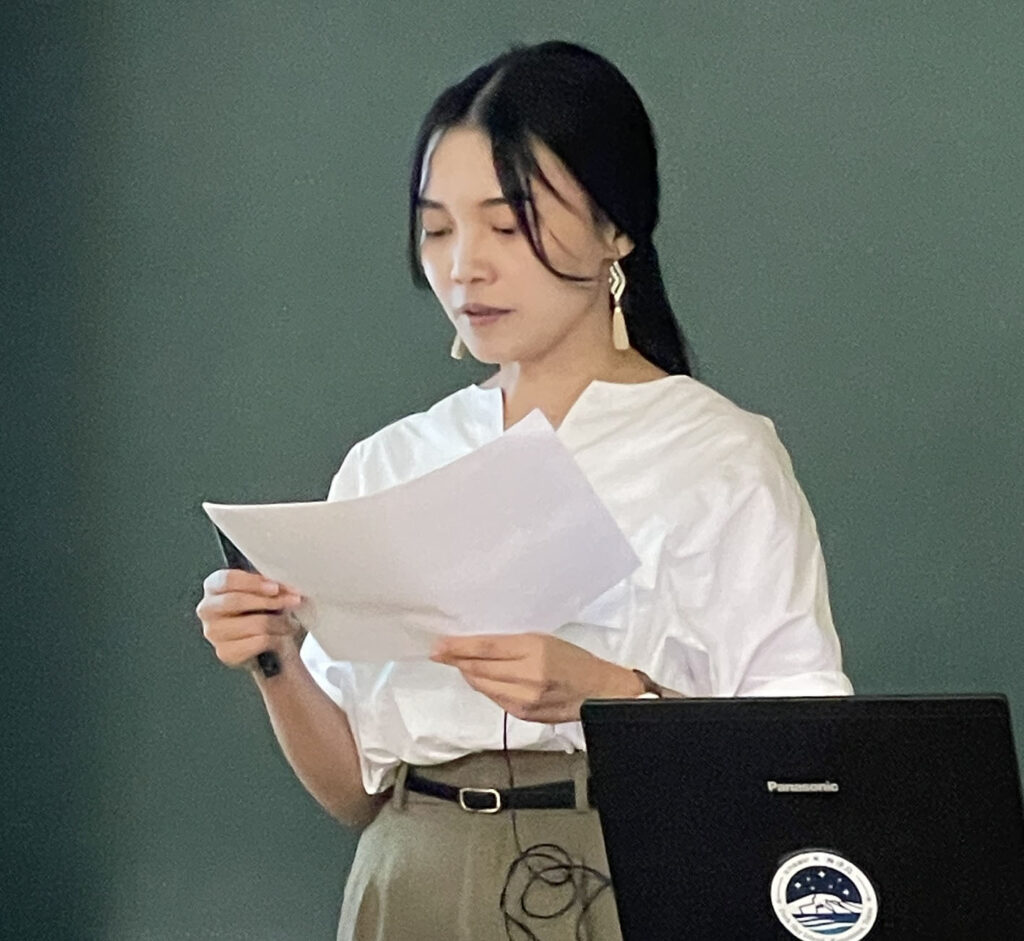
今大会のプログラムは、以下のURLより閲覧できます。関心のある方は、ぜひご覧下さい。
https://jpars.org/conf-past.html
なお、発表要旨は、『宗教研究』94巻別冊(オンライン公開)に掲載されています。
https://jpars.org/data/files/separate_volume/vol_98.pdf
(文責:小前ひろみ・芳賀徳仁・江原知華)
